-
- 掲示板
掲示板
BBSイラスト投稿や質問・連絡事項の
書き置きとしてご利用ください◎
海
海雲さん (7w8zzru6)2021/4/18 21:52 (No.74769)削除ハリスの父親視点でのソロルです。
もっと、ボキャと構成力があればなぁ…
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
私の父が亡くなった日は唐突だった。医師によると心筋梗塞が原因らしい。もともと煙草が好きでいつか倒れるとは思っていたが、まさか69歳で亡くなるだなんて思いもよらなかった。
「やっと死んだか…」
そんな悪態を吐きながらも、私は泣いていた。押さえようとも涙が止まらないのだ。恐らく私は心から、彼の死を惜しんでいるのだろう。こうしてはいられまいと、私はすぐに家族に、父の知り合いらに訃報の手紙を出した。私が言うのもなんだが、彼は良い人であったので他人からはとても信頼されていた。そのため多くの人々が悲しむことだろう。しかし、その中でも娘が一番悲しむことになると思う。なんせ、父が最も愛したのは娘だったし、娘も彼を非常に愛していたからだ。
こう言うのはまずいだろうが、タイミングは良かった。なぜなら、明後日には彼女の通う学校が夏休みを迎えるからだ。また、もしタイミングが悪ければ、寮生活を送る彼女は葬儀に参加できず、さらに深い悲しみを背負っていくことになるだろうからだ。
ふと、気づけば涙は引いていた。そろそろ物思いにふけるのはやめにしよう。明日からは葬儀の打ち合わせなどで忙しくなる。周りに余計な気を使わせないように、強く構えていよう。
あれから数日が経ち、ついに葬儀の日が訪れた。葬儀の打ち合わせはちょっとした諍いを除けば、思っていたよりもはるかに円滑に進んだ。どうやら父が死んだ後にどう弔って欲しいか伝えていたらしい。本当に抜かりのない人物だ。
結局、38名余りの人が花束を送ってくれ、改めて父はとても信頼され、愛されていたのだと思った。
葬儀に集まったのは私たち家族と、妹の家族、そして父と親しくしていた同僚らだった。教会に集まった我々は父の天国での生活が幸福であることを祈り、賛美歌を歌った。続いて牧師が聖書を引用して彼の人生を語る。個人的に何も知らないお前が父の何を知っている、と説いてやりたいのだが、そういうしきたりなのだと不満ながらも納得して聞き入っていた。
胡散臭い語りが終われば、会話を交えながら火葬場へ移動し始めた。皆、笑いまじりに、だけどどこか哀愁を感じさせるように父との思い出を語り合っていた。
ふと、ハリスはどうしているのか気になり、そちらに目をやる。すると、教会のステンドグラスから指してくる光を避けるように端に沿って歩いているのが見えた。表情はベールでよく見えなかったが、彼女の周りの暗い空気も相まって落ち込んでいるのだと悟った。
「……大丈夫か。やっと夏休みだと言うのに急にこんなことになって……その、なんだ…哀しいのではないか」
「大丈夫です。…哀しくはありません。なんならこの場に立ち会えてよかったと安堵して、落ち着いています。」
不意に声をかけた。しかし、うまく言葉が思い浮かばず、手探りで慎重に言葉を選びながら話した。それに応えた彼女の声からは哀しみや落ち込みなどと言った負の感情を一切感じさせなかった。むしろ、力強さや温かさを感じた。私は自分の娘を測りかねていたようだ。それを知り、娘が強く成長してくれたという嬉しさと同時に、自分の元を旅立つ日が近いことを知り淋しさを感じた。
父の遺言は、『火葬し頭骨を墓に入れて、他の骨は葬儀に立ち会った者が持っていてくれ』というイギリスでは異端なものだった。そもそも骨を持っていくという行為自体信じられないもので、何度か牧師に散骨か埋葬にしてくれと頼み込んだのだが「本人の意思なので…」と、断られ、妻に慰められながら渋々その意見を飲んだものだ。本当にあの人は傾いていた。
葬儀に参加している者が全員火葬場に着けば、後から蓋の開けられた棺が運ばれてきた。そこからは眠っている父の顔が覗けた。その表情は死ぬ間際に相当苦しんだことを全く悟らせることはなく、父として、祖父としての威厳を感じさせた。周りの人らも同様に覗いていたようで、皆の顔からは憂いを感じとることができた。
すると、牧師らによって棺の蓋が閉じられ台車に乗せられた。そして、それは火葬炉の中に入れられた。
しばらく、沈黙が訪れた。私は再びハリスの方へ目線を向ける。相変わらず彼女の表情は隠されており見えない。しかし、ただ一点、火葬炉に視線を向けていることは分かった。
「…大丈夫か?……その…ああ…えっと…」
何も言葉が浮かばない。彼女が何を思っているのかさえも。だから、考えなしに声をかけては行き詰まってしまい、つい癖で顳顬を押さえる。そんな情けない私を見て、口元に手を持って行き笑って見せる。
「……心配しないでください。お爺様の顔をもう見れないのはとても哀しいですが……いつかはこうなっていたんです。だから、もう大丈夫です。」
その言葉を聞いて安堵した。同時に私はなんて過保護なんだろうと自身に呆れを抱いた。その後は一問一答の会話とは言い切れないやりとりが続いた。
そんなやりとりを繰り返して数分後。火葬が終わったようで、火葬炉の扉が開かれる。そして、教会の人らが中の台車に乗った棺を運び出してくる。焦げ臭い匂いはなく、本当に火葬したのか疑問に思った。
それも束の間、牧師が棺の蓋を開けてからそんな疑問は消え失せた。中に父の姿は影も形もなく、そこには白い粉末と頭骨など骨があった。初見時にこれが父だったと知らされなければ、誰の骸か気づくことはないだろう。私はただこんな考察をして冷静さを保っていたのだが、妹は涙を流していた。そしてショックのあまり口元を押さえながら膝から崩れた。それを彼女の夫が支え一言、すいませんと言って火葬場から出て行く。
しかし、儀式は続くようで数個の白い箱が持ってこられた。
「それでは骨上げを開始しますので、トーマスさん。ご遺骨をこちらの箱に入れてください」
名前が呼ばれるとはっ、と我に帰る。どうやら無意識のうちに放心していたらしい。数秒の時間差で反応すればへこへこと頭を動かしながら、呼びかけてきた牧師の元へ向かう。
ここでさっきの言葉を思い返した。遺骨を箱に入れる。その言葉に少し混乱した。素手でこの骸に触れるのか、と。困り果て、妻がいるの方を見れば怪訝な表情を浮かべ、首を傾げていた。牧師の方に目線を向け、目で訴えると「そのままご遺骨を拾うだけですよ」との応えが帰ってきた。そう言われても、触れるのには抵抗があり、手を伸ばそうにも伸ばせずにいた。
そんな中、私の横から手が伸ばされた。その手は一切の躊躇もなく、父の頭骨を拾い上げた。視線をその手の持ち主の方へと向ける。それは私の娘、ハリスだった。
彼女は惹きつけるような青い目を曇らせ、黒く短い髪を火葬炉からくる微かな風になびかせていた。髪と共に扇がれたベールの合間からはようやく彼女の表情を拝めた。そのほおは紅潮させられており、妖艶な微笑みを浮かべていた。
「ああ、お爺様。私の愛おしき人よ。もうあの優しい表情を拝めないのは大層心苦しいです……しかし……こうやって間近であなたの顔を見られて…私は…心から嬉しいですよ」
彼女は無作法にも手順を無視して、父の頭骨を拾い上げ、目の前に持っていった。そして最後には自身の額をそれの額に押し当てる。
実に異端で酷く冒涜的なその様子に私は畏怖の念を抱くことは出来なかった。むしろ、その光景に美しさや尊さを見出し、恍惚として見入ってしまった。
「しばらくの別れとなりますが……先に向こうで待っていてください。いずれ私もそちらに行きますから……ね。そして……見守っててくださいね。だってこれからはずっと一緒なんですから」
囁くように、だが脳裏に焼きつきそうなほどねっとりと頭骨に言葉を注ぎ込む。私の前を通り過ぎると、指定されていた箱にそれを入れる。再び棺に向き直れば1尺ほどはありそうな骨を手にとってその頭骨に見せつけるようにして笑う。
優しく静かに、華麗に、狂気的に、冒涜的に、だけどどこか哀しげに。
あれから15年経った。ハリスは学校を卒業してすぐに我々の元を出て行った。私は彼女が一人で大丈夫だろうかと心配し気が気でなかった。
2年程後に母校の教師になったことが綴られた手紙が届き、胸を撫で下ろしたものだ。
父は潮の風を浴びながら、誰かが植えたキキョウに囲まれながら眠っている。
毎年、私は彼が亡くなった日にそこを訪れている。相変わらずその場に立ち入るとあの葬式でのことを思い出す。それは妻も同様のようで、その苦虫を噛み潰したような顔を見れば、幻想や夢として捉えていた私を何度も現実に引き戻させた。
しかし、数年前から彼女はそこに立ち入るのを拒むようになった。だから、今年も私一人でこの場所を訪れた。花束を抱えて、聖堂に入り右折し林の中に入る。
しばらく歩いて林を抜けた時、先客がいることに気づいた。
その人物は黒く長い髪を束ねては肩に乗せて垂らし、苔のように濃い緑色のローブを纏っていた。考えるより先に答えが出て、声が出る。
「ハリス。久しぶりだな」
「……ええ、御無沙汰しております。お父様」
少しの間を置いて、振り向いて私に女の子らしく、しかしどこか大人っぽい可憐な笑みを浮かべて見せた。
手には汚れた雑巾を持っており、墓石を掃除していたことが窺える。
スカートの埃を払いながら立ち上がると、近くのバケツに雑巾を放り投げる。
彼女の身長はあの時と比べかなり伸びており、背伸びをされたら恐らく抜かれるだろう程までに大きくなっていた。
「私が来るときには毎年掃除されていたんですが、お父様が掃除していたんですね」
「まあな。そこまで面倒なものではないしな。そういうお前はわざわざ手作業で掃除か」
納得がいった、という風に微笑んだ彼女を見ては肯定して見せる。
実際、人目を気をつければ杖の二振りで掃除が終わる。逆に私は何故魔法を行使しないのか遠回りで尋ねる。
「まあ…はい。そちらの方が長くお爺様の側にいれますし」
笑みを崩さずに彼女は応える。
彼女が自身の祖父に対して抱くモノは恐ろしいものだと思ったが、同時にとても純粋で美しいものだと感じてしまう。
そんな自分にやや嫌悪感を抱いていると、彼女がローブの内側から赤い薔薇の花束を出せば蹲み込んで墓石のもとに置き、暫くそこを見つめた。
それに連れられるように自分も蹲み込んで花束を置く。
「それでは、私は行きますね。…ジゼルが待ってますので」
ハリスは再び立ち上がってそう告げた。私が立ち上がったときには、すでにバケツを拾って2、3歩離れていた。
「ああ……ハリス、いつか…お前の薔薇は黄色に染まるのだろうか?」
その問いかけが通じたのか、彼女はピタッと急にその足を止めて首をこちらに向ける。数秒だけ、沈黙が訪れる。それはとても長いものだと感じれた。風が吹き始め、キキョウが揺れる。
「……ふふ。なりませんよ。……青い薔薇が私の目の前で咲かない限りは」
そう、応えては弱々しくも美しい笑みを浮かべて見せる。そして、前を向いて林の奥へと向かって行った。私は彼女の最後の言葉を受け止めると「そうか」と呟いた。
もっと、ボキャと構成力があればなぁ…
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
私の父が亡くなった日は唐突だった。医師によると心筋梗塞が原因らしい。もともと煙草が好きでいつか倒れるとは思っていたが、まさか69歳で亡くなるだなんて思いもよらなかった。
「やっと死んだか…」
そんな悪態を吐きながらも、私は泣いていた。押さえようとも涙が止まらないのだ。恐らく私は心から、彼の死を惜しんでいるのだろう。こうしてはいられまいと、私はすぐに家族に、父の知り合いらに訃報の手紙を出した。私が言うのもなんだが、彼は良い人であったので他人からはとても信頼されていた。そのため多くの人々が悲しむことだろう。しかし、その中でも娘が一番悲しむことになると思う。なんせ、父が最も愛したのは娘だったし、娘も彼を非常に愛していたからだ。
こう言うのはまずいだろうが、タイミングは良かった。なぜなら、明後日には彼女の通う学校が夏休みを迎えるからだ。また、もしタイミングが悪ければ、寮生活を送る彼女は葬儀に参加できず、さらに深い悲しみを背負っていくことになるだろうからだ。
ふと、気づけば涙は引いていた。そろそろ物思いにふけるのはやめにしよう。明日からは葬儀の打ち合わせなどで忙しくなる。周りに余計な気を使わせないように、強く構えていよう。
あれから数日が経ち、ついに葬儀の日が訪れた。葬儀の打ち合わせはちょっとした諍いを除けば、思っていたよりもはるかに円滑に進んだ。どうやら父が死んだ後にどう弔って欲しいか伝えていたらしい。本当に抜かりのない人物だ。
結局、38名余りの人が花束を送ってくれ、改めて父はとても信頼され、愛されていたのだと思った。
葬儀に集まったのは私たち家族と、妹の家族、そして父と親しくしていた同僚らだった。教会に集まった我々は父の天国での生活が幸福であることを祈り、賛美歌を歌った。続いて牧師が聖書を引用して彼の人生を語る。個人的に何も知らないお前が父の何を知っている、と説いてやりたいのだが、そういうしきたりなのだと不満ながらも納得して聞き入っていた。
胡散臭い語りが終われば、会話を交えながら火葬場へ移動し始めた。皆、笑いまじりに、だけどどこか哀愁を感じさせるように父との思い出を語り合っていた。
ふと、ハリスはどうしているのか気になり、そちらに目をやる。すると、教会のステンドグラスから指してくる光を避けるように端に沿って歩いているのが見えた。表情はベールでよく見えなかったが、彼女の周りの暗い空気も相まって落ち込んでいるのだと悟った。
「……大丈夫か。やっと夏休みだと言うのに急にこんなことになって……その、なんだ…哀しいのではないか」
「大丈夫です。…哀しくはありません。なんならこの場に立ち会えてよかったと安堵して、落ち着いています。」
不意に声をかけた。しかし、うまく言葉が思い浮かばず、手探りで慎重に言葉を選びながら話した。それに応えた彼女の声からは哀しみや落ち込みなどと言った負の感情を一切感じさせなかった。むしろ、力強さや温かさを感じた。私は自分の娘を測りかねていたようだ。それを知り、娘が強く成長してくれたという嬉しさと同時に、自分の元を旅立つ日が近いことを知り淋しさを感じた。
父の遺言は、『火葬し頭骨を墓に入れて、他の骨は葬儀に立ち会った者が持っていてくれ』というイギリスでは異端なものだった。そもそも骨を持っていくという行為自体信じられないもので、何度か牧師に散骨か埋葬にしてくれと頼み込んだのだが「本人の意思なので…」と、断られ、妻に慰められながら渋々その意見を飲んだものだ。本当にあの人は傾いていた。
葬儀に参加している者が全員火葬場に着けば、後から蓋の開けられた棺が運ばれてきた。そこからは眠っている父の顔が覗けた。その表情は死ぬ間際に相当苦しんだことを全く悟らせることはなく、父として、祖父としての威厳を感じさせた。周りの人らも同様に覗いていたようで、皆の顔からは憂いを感じとることができた。
すると、牧師らによって棺の蓋が閉じられ台車に乗せられた。そして、それは火葬炉の中に入れられた。
しばらく、沈黙が訪れた。私は再びハリスの方へ目線を向ける。相変わらず彼女の表情は隠されており見えない。しかし、ただ一点、火葬炉に視線を向けていることは分かった。
「…大丈夫か?……その…ああ…えっと…」
何も言葉が浮かばない。彼女が何を思っているのかさえも。だから、考えなしに声をかけては行き詰まってしまい、つい癖で顳顬を押さえる。そんな情けない私を見て、口元に手を持って行き笑って見せる。
「……心配しないでください。お爺様の顔をもう見れないのはとても哀しいですが……いつかはこうなっていたんです。だから、もう大丈夫です。」
その言葉を聞いて安堵した。同時に私はなんて過保護なんだろうと自身に呆れを抱いた。その後は一問一答の会話とは言い切れないやりとりが続いた。
そんなやりとりを繰り返して数分後。火葬が終わったようで、火葬炉の扉が開かれる。そして、教会の人らが中の台車に乗った棺を運び出してくる。焦げ臭い匂いはなく、本当に火葬したのか疑問に思った。
それも束の間、牧師が棺の蓋を開けてからそんな疑問は消え失せた。中に父の姿は影も形もなく、そこには白い粉末と頭骨など骨があった。初見時にこれが父だったと知らされなければ、誰の骸か気づくことはないだろう。私はただこんな考察をして冷静さを保っていたのだが、妹は涙を流していた。そしてショックのあまり口元を押さえながら膝から崩れた。それを彼女の夫が支え一言、すいませんと言って火葬場から出て行く。
しかし、儀式は続くようで数個の白い箱が持ってこられた。
「それでは骨上げを開始しますので、トーマスさん。ご遺骨をこちらの箱に入れてください」
名前が呼ばれるとはっ、と我に帰る。どうやら無意識のうちに放心していたらしい。数秒の時間差で反応すればへこへこと頭を動かしながら、呼びかけてきた牧師の元へ向かう。
ここでさっきの言葉を思い返した。遺骨を箱に入れる。その言葉に少し混乱した。素手でこの骸に触れるのか、と。困り果て、妻がいるの方を見れば怪訝な表情を浮かべ、首を傾げていた。牧師の方に目線を向け、目で訴えると「そのままご遺骨を拾うだけですよ」との応えが帰ってきた。そう言われても、触れるのには抵抗があり、手を伸ばそうにも伸ばせずにいた。
そんな中、私の横から手が伸ばされた。その手は一切の躊躇もなく、父の頭骨を拾い上げた。視線をその手の持ち主の方へと向ける。それは私の娘、ハリスだった。
彼女は惹きつけるような青い目を曇らせ、黒く短い髪を火葬炉からくる微かな風になびかせていた。髪と共に扇がれたベールの合間からはようやく彼女の表情を拝めた。そのほおは紅潮させられており、妖艶な微笑みを浮かべていた。
「ああ、お爺様。私の愛おしき人よ。もうあの優しい表情を拝めないのは大層心苦しいです……しかし……こうやって間近であなたの顔を見られて…私は…心から嬉しいですよ」
彼女は無作法にも手順を無視して、父の頭骨を拾い上げ、目の前に持っていった。そして最後には自身の額をそれの額に押し当てる。
実に異端で酷く冒涜的なその様子に私は畏怖の念を抱くことは出来なかった。むしろ、その光景に美しさや尊さを見出し、恍惚として見入ってしまった。
「しばらくの別れとなりますが……先に向こうで待っていてください。いずれ私もそちらに行きますから……ね。そして……見守っててくださいね。だってこれからはずっと一緒なんですから」
囁くように、だが脳裏に焼きつきそうなほどねっとりと頭骨に言葉を注ぎ込む。私の前を通り過ぎると、指定されていた箱にそれを入れる。再び棺に向き直れば1尺ほどはありそうな骨を手にとってその頭骨に見せつけるようにして笑う。
優しく静かに、華麗に、狂気的に、冒涜的に、だけどどこか哀しげに。
あれから15年経った。ハリスは学校を卒業してすぐに我々の元を出て行った。私は彼女が一人で大丈夫だろうかと心配し気が気でなかった。
2年程後に母校の教師になったことが綴られた手紙が届き、胸を撫で下ろしたものだ。
父は潮の風を浴びながら、誰かが植えたキキョウに囲まれながら眠っている。
毎年、私は彼が亡くなった日にそこを訪れている。相変わらずその場に立ち入るとあの葬式でのことを思い出す。それは妻も同様のようで、その苦虫を噛み潰したような顔を見れば、幻想や夢として捉えていた私を何度も現実に引き戻させた。
しかし、数年前から彼女はそこに立ち入るのを拒むようになった。だから、今年も私一人でこの場所を訪れた。花束を抱えて、聖堂に入り右折し林の中に入る。
しばらく歩いて林を抜けた時、先客がいることに気づいた。
その人物は黒く長い髪を束ねては肩に乗せて垂らし、苔のように濃い緑色のローブを纏っていた。考えるより先に答えが出て、声が出る。
「ハリス。久しぶりだな」
「……ええ、御無沙汰しております。お父様」
少しの間を置いて、振り向いて私に女の子らしく、しかしどこか大人っぽい可憐な笑みを浮かべて見せた。
手には汚れた雑巾を持っており、墓石を掃除していたことが窺える。
スカートの埃を払いながら立ち上がると、近くのバケツに雑巾を放り投げる。
彼女の身長はあの時と比べかなり伸びており、背伸びをされたら恐らく抜かれるだろう程までに大きくなっていた。
「私が来るときには毎年掃除されていたんですが、お父様が掃除していたんですね」
「まあな。そこまで面倒なものではないしな。そういうお前はわざわざ手作業で掃除か」
納得がいった、という風に微笑んだ彼女を見ては肯定して見せる。
実際、人目を気をつければ杖の二振りで掃除が終わる。逆に私は何故魔法を行使しないのか遠回りで尋ねる。
「まあ…はい。そちらの方が長くお爺様の側にいれますし」
笑みを崩さずに彼女は応える。
彼女が自身の祖父に対して抱くモノは恐ろしいものだと思ったが、同時にとても純粋で美しいものだと感じてしまう。
そんな自分にやや嫌悪感を抱いていると、彼女がローブの内側から赤い薔薇の花束を出せば蹲み込んで墓石のもとに置き、暫くそこを見つめた。
それに連れられるように自分も蹲み込んで花束を置く。
「それでは、私は行きますね。…ジゼルが待ってますので」
ハリスは再び立ち上がってそう告げた。私が立ち上がったときには、すでにバケツを拾って2、3歩離れていた。
「ああ……ハリス、いつか…お前の薔薇は黄色に染まるのだろうか?」
その問いかけが通じたのか、彼女はピタッと急にその足を止めて首をこちらに向ける。数秒だけ、沈黙が訪れる。それはとても長いものだと感じれた。風が吹き始め、キキョウが揺れる。
「……ふふ。なりませんよ。……青い薔薇が私の目の前で咲かない限りは」
そう、応えては弱々しくも美しい笑みを浮かべて見せる。そして、前を向いて林の奥へと向かって行った。私は彼女の最後の言葉を受け止めると「そうか」と呟いた。
海
海雲さん (7vp018na)2021/4/19 06:47参考までに花言葉
赤い薔薇:「あなたを愛してます」「熱烈な恋」「愛情」
黄色い薔薇:「愛情の薄らぎ」「嫉妬」
青い薔薇:「不可能」「奇跡」
キキョウ:「永遠の愛」「変わらぬ愛」
赤い薔薇:「あなたを愛してます」「熱烈な恋」「愛情」
黄色い薔薇:「愛情の薄らぎ」「嫉妬」
青い薔薇:「不可能」「奇跡」
キキョウ:「永遠の愛」「変わらぬ愛」
返信
返信1
初
初さん (7vc5lpmk)2021/4/12 22:32 (No.74225)削除エリック「2人とも、もうちょっとくっついてください!あ、Evil先生、くっつきすぎです被ります。ほら、笑ってー、ちーず、。」
ぱしゃ ッ
妄想です。誰がどう見ても、司書さんと森番さんです🥰🥰🥰
ぱしゃ ッ
妄想です。誰がどう見ても、司書さんと森番さんです🥰🥰🥰
 題「仲良しな2人」
題「仲良しな2人」エリック作
返信
返信0
永
永さん (7vdlhl0y)2021/4/11 14:58 (No.74070)削除誰がなんと言おうとこれは司書さんです。
絵ぢから不足💢💢💢💢💢
絵ぢから不足💢💢💢💢💢
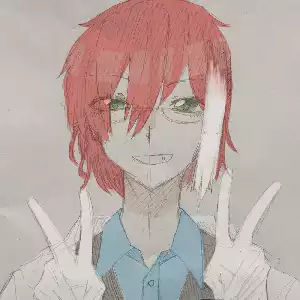 ミ゚ッッッ
ミ゚ッッッ返信
返信0
湯
湯気さん (7vg0k6ge)2021/4/11 00:03 (No.74006)削除森番さんごめんなさい 。の絵 。( 成りの絵を描けなかッた )( 懺悔 )
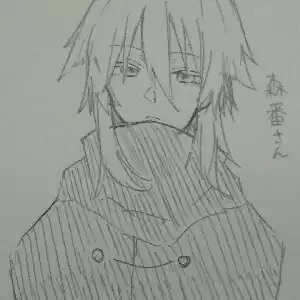
 なかよし ( ???? )
なかよし ( ???? )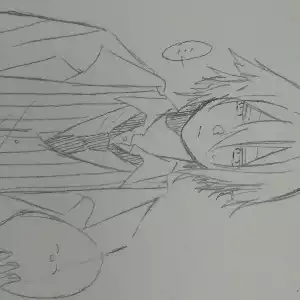 イベで着てほしかッた
イベで着てほしかッた返信
返信0
永
永さん (7vdlhl0y)2021/4/10 21:00 (No.73972)削除色塗り中途半端で申し訳ない感じの初ちゃん宅のシャルロットちゃんです。髪の毛とお肌と目を塗って満足しました。
左側に自宅のレティシアいる予定だったけど溢れ出る「 ナンカチガウ… 」感に負けて没になったのでスクショ供養。
左側に自宅のレティシアいる予定だったけど溢れ出る「 ナンカチガウ… 」感に負けて没になったのでスクショ供養。
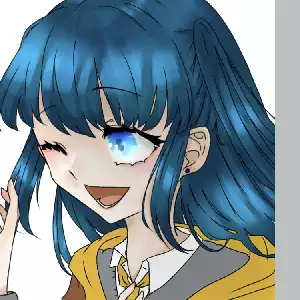
返信
返信0
鰤
鰤家さん (7vuraf3g)2021/4/8 23:43 (No.73822)削除バランスとか何も考えずにほぼ一発書きをして結果一発書きよりも酷いものになったCheckです
※ 消します
※ 消します
 お前は俺の性癖の70%を詰めたキャラなのだからもっと自覚を持て(暴論)
お前は俺の性癖の70%を詰めたキャラなのだからもっと自覚を持て(暴論)返信
返信0
非
非さん (7vusqvb4)2021/4/8 23:21 (No.73820)削除初さんとこのヘーゼルくんです〜!色塗れてないけどごめんね☺️🙏

返信
返信0
初
初さん (7vc5lpmk)2021/4/6 21:56 (No.73636)削除メーガンちゃんと司書さんです!
今回あまりにも酷いので、削除する可能性が高いです。 また描き直します😭😭
あ、いつも通り落書きクォリティ((
ほんとに納得いかないので、まじで描き直したい。
今回あまりにも酷いので、削除する可能性が高いです。 また描き直します😭😭
あ、いつも通り落書きクォリティ((
ほんとに納得いかないので、まじで描き直したい。
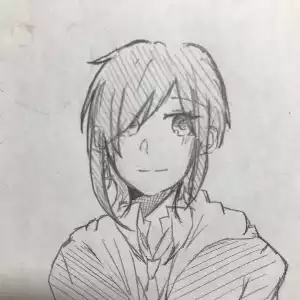 メーガンちゃん!
メーガンちゃん!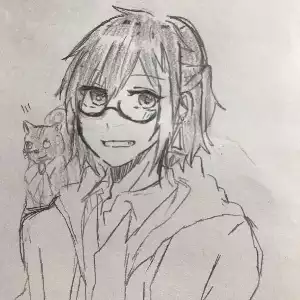 司書さん!
司書さん!返信
返信0
湯
湯気さん (7vg0k6ge)2021/4/5 23:41 (No.73564)削除シャルロットちャんと司書
 カワイイネッ
カワイイネッ シ - ッ !
シ - ッ !返信
返信0
初
初さん (7vc5lpmk)2021/4/5 21:27 (No.73542)削除三角関係になったらどうするかの話。
ヘーゼル に ドン引きする シャルロット
ヘーゼル に ドン引きする シャルロット


初
初さん (7vc5lpmk)2021/4/5 21:34不穏なヘーゼル
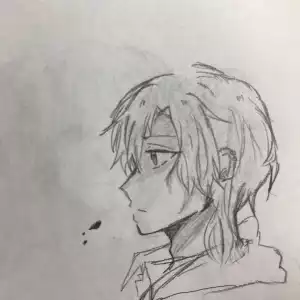
返信
返信1